
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で、即戦力として働ける外国人材を受け入れるために設けられた制度です。
技能実習を終えて次のステップに進む方、日本の企業でキャリアを築きたい方にとって、大きなチャンスとなります。
しかし、「どんな試験が必要なの?」「日本語のレベルは?」「企業側はどんな準備をしなければならない?」
──そんな不安や疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
このページでは、特定技能の仕組み・要件・必要書類・支援体制・企業側の義務までまとめて解説しています。
外国人の方も受入企業の方も、ぜひこのページを読み進めながら準備を進めてみてください。
▶ このページでわかること(気になるところから読めます!)
在留資格「特定技能」とは?
在留資格「特定技能」とは?
「特定技能」は、日本で深刻な労働力不足が生じている特定の産業分野において、外国人労働者を受け入れるために設けられた在留資格です。「Specified Skilled Worker」の頭文字をとってSSWと略されることもあります。2019年に創設されて以来、即戦力となる技能を持った外国人労働者が日本で活躍できる機会を提供しています。この在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
【特定技能1号】
一定の技能や知識を有し、即戦力として働ける外国人が対象です。2025年1月現在、特定の16分野で就労が認められており、最長5年間日本で働くことができます。
【特定技能2号】
特定技能1号よりもさらに高度な技能を有する外国人が対象で、就労分野は特定の11分野です。この資格では家族の帯同が可能で、在留期間の更新に制限がなく、長期的に日本で働くことができます。
【深刻な労働力不足が生じている特定の産業分野とは?-2025年1月現在-】
●介護
●ビルクリーニング
●工業製品製造業
機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理・紙器/段ボール箱製造・コンクリート製品製造・RPF製造・陶磁器製品製造・印刷/製本・紡織製品製造・縫製
●建設
・土木・建築・ライフライン
●造船・舶用工業
造船・舶用機械・舶用電気電子機器
●自動車整備
●航空
空港グランドハンドリング・航空機整備
●宿泊
●自動車運送業
バス運転者・タクシー運転者・トラック運転者
●鉄道
軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員
●農業
耕種農業・畜産農業
●漁業
・漁業・養殖業
●飲食料品製造業
●外食業
●林業
●木材産業
特定技能外国人を受け入れるための要件とは?
特定技能外国人を受け入れるための要件とは?
【特定技能外国人が備える要件】
●技能水準の確認(特定技能1号)
希望する分野で即戦力として働ける技能・知識を有していることが求められます。その証明として、所管省庁が指定する試験実施機関による「特定技能1号評価試験」に合格している必要があります。
※技能試験は分野ごとに内容・基準が異なります。
※「特定技能として従事しようとする業務」と「技能実習2号の職種・作業」に関連性がある場合には、技能評価試験は免除となります。
●技能水準の確認(特定技能2号)
特定技能1号とは異なり、より高度な技能・経験を保有していることが前提となります。その証明として、所管省庁が指定する試験実施機関による「特定技能2号評価試験」に合格している必要があり、加えて多くの分野では主に管理的立場で一定の経験年数の証明が求められます。
※技能試験は分野ごとに内容・基準が異なります。
※介護分野では、在留資格「介護」があるため、特定技能2号在留資格はありません。
●日本語能力の証明
業務を遂行するために必要な日本語能力を証明する必要があります。
原則として、日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格することが条件となります。
※介護分野では「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。
※技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語試験も免除されます。
※特定技能2号では、試験等での日本語力証明の確認は不要となっています。
●年齢
申請者は18歳以上であることが求められます。
●技能実習制度から特定技能1号へ移行する場合
技能実習2号を良好に修了した人は、特定技能として従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性がある場合には、特定技能1号の資格に転換することが可能です。
●その他
退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人でないこと、本人又はその親族などが保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられていないこと等が条件となります。
【受入れ企業の主な要件】
●受入れ企業による産業分野別協議会への加入
特定技能制度の適切な運用を図るため、各特定産業分野ごとに所管省庁が協議会を設置しており、受入れ企業は、該当するこれらの協議会に加入する必要があります。この協議会は、受入れ機関、業界団体、関係省庁などで構成され、特定技能外国人の受入れに関する制度の周知や法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足状況の把握と対応策の検討などを行っています。
●適正な雇用契約を締結していること
特定技能外国人と受入企業の間で、労働条件、給与、福利厚生、労働時間などが適切に定められた雇用契約を結ぶ必要があります。
●受入れ機関自体が適切であること
税金、社会保険料等の納付を適切に行なっているなど法令等を遵守し、また禁固以上の刑に処せられた者等の欠格事由に該当しないこと、外国人を支援する体制があること、外国人を支援する計画が適切であることなどが求められます。
特定技能外国人の受入れ/支援体制
特定技能外国人の受入れ/支援体制
特定技能1号外国人を受け入れる企業には、単に雇用契約を結ぶだけでなく、生活支援・相談体制の整備など、多面的な支援義務があります。これは、外国人材が安心して日本で働き、定着できる環境を整えるための仕組みです。具体的には、入国時の空港送迎や住宅確保、生活オリエンテーション、日本語学習支援、各種相談窓口の設置など、10項目にわたる支援を行うこととなります。これらの支援は、企業が自ら行うことも、登録支援機関に委託することも可能です。支援体制を適切に整えることは、外国人材の定着率や職場の安定性にも大きく関わってきます。
【特定技能外国人への支援項目】
特定技能外国人の活動を安定的かつ円滑に進めることができるよう、以下の支援項目について支援計画を作成し、この計画に基づいて支援を行います。なお、特定技能2号外国人については支援の対象とはならないため、ここでは特定技能1号外国人就労者への支援項目をご紹介します。
● 事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
● 出入国する際の送迎
- 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
- 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
●住居確保・生活に必要な契約支援
- 連帯保証人になる・社宅を提供する等
- 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
●生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
●公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
● 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
●相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
●日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
● 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
● 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
【法令に基づく受入れ企業による届出/報告義務】
受入れ企業は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。受入れ企業が届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。登録支援機関についても、指導や登録の取消しの対象となります。
●随時の届出
- 特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
- 支援計画の変更に係る届出
- 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
- 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
- 外国人の雇い入れ時または離職時における氏名や在留資格等の情報のハローワークへの届出
●定期の届出
- 特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出
- 支援計画の実施状況に関する届出
【支援の実施方法(自社支援/登録支援機関への委託)】
特定技能外国人1号を受け入れる場合、受入れ企業は支援の実施について、自社で支援を行うか、あるいはもしくは登録支援機関へ委託するかを選択できます。
●受入れ企業が自社で全て行う場合
受入れ企業は、一定の条件を満たした場合、自社にて支援を行うことができます。受入企業は以下の条件を満たす必要があります。
- 過去2年間に中長期在留者(注)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること。または支援責任者及び支援担当者に過去5年間に2年以上の中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験があること
- 受入れ/支援体制が確保されていること
- 支援の実施に係る文書の作成・保管ができること
- 分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に適合していること
- 支援責任者(担当者)の中立性が確保されていること
●登録支援機関に支援項目の全部または一部を委託して行う場合
特定技能外国人の支援内容は多く、一定の時間と労力が必要となります。また、関係法令の改正などの動向を注視しながら支援業務を的確に行うことも容易ではありません。自社支援で行う場合、これらの業務ために社内のリソースを充てなければならず、それに伴った人件費も予想されます。そのため、現状で自社で十分な支援体制が構築できない場合には、支援項目の全部または一部を委託して行うことができます。
●登録支援機関に支援を委託する場合の費用
- 費用は法定で定められておらず各機関ごとに異なる
- 一般的には、1人あたり月額2〜4万円程度が目安となり、初期支援(空港送迎や住宅手配等)で3〜5万円程度の初期費用がかかるケースが多い
- 詳細は、支援範囲や受入人数、追加オプションの有無によって変動する
●自社で支援する場合と登録支援機関に委託する場合のメリット/デメリット
特定技能外国人の支援について、自社支援が適しているか、登録支援機関への委託が適しているかは、受入れ企業個別の状況により異なります。特に自社支援導入については、支援体制の構築に必要な人員体制や費用、また今後の人材採用の進め方などを考慮し慎重に判断する必要があります。
| 項目 | 自社で支援する場合 | 登録支援機関に委託する場合 |
|---|---|---|
| コスト | 委託料が不要でコストを抑えられる | 月2〜4万円/人+初期費用が発生 |
| 柔軟性 | 社内事情に合わせた支援が可能 | 機関の標準サービスに沿った支援 |
| 専門性 | 社員に知識・経験が必要 | 法定支援に精通した専門家が対応 |
| 負担 | 支援体制構築や報告業務の負担大 | 生活支援や定期面談を外部任せにできる |
| 外国人との関係性 | 直接サポートで信頼関係を築きやすい | 支援が外部任せになり距離が生じることも |
| 多言語・緊急対応 | 社内対応が必要で課題になりやすい | 多言語・24時間体制が整備されている場合が多い |
| 人材採用 | 自社の技能実習から移行した人材を引き続き雇用する場合を除き、自社で特定技能外国人の採用機能を持たない場合は、人材紹介会社や海外の送り出し機関等に個別に依頼して求人活動を行う必要あり | 雇用条件の設定、人材の募集、面接機会のアレンジ、採用に伴う雇用契約締結、支援計策作成、事前ガイダンス、入管への申請、さらに実際の支援実施まで、一貫したサービスの提供を受けることが可能となる |
特定技能ビザ申請に必要な書類と審査期間は?
特定技能ビザ申請に必要な書類と審査期間は?
【在留資格認定証明書交付申請必要書類(特定技能1号の例)】
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 複数の申請人について同時申請する場合は申請人名簿
- 証明写真
申請人に関する必要書類
所属機関の規模等に応じた次のいずれかの必要書類
分野に関する必要書類
介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船/舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・自動車運送業・鉄道・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・林業・木材産業
【在留資格変更許可申請必要書類(特定技能1号の例)】
共通書類
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合は申請人名簿
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
- 申請人のパスポート及び在留カード 提示
申請人に関する必要書類
所属機関の規模等に応じた次のいずれかの必要書類
分野に関する必要書類
介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船/舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・自動車運送業・鉄道・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・林業・木材産業
【審査期間】
「特定技能」在留資格の審査期間は、通常1か月から3か月程度かかります。ただし、申請する地域や時期、書類の不備や追加確認が必要な場合は、審査期間がさらに延びることがあります。
特定技能制度に関するよくある質問(FAQ)
特定技能制度に関するよくある質問(FAQ)
-
特定技能とは何ですか?
-
特定産業分野の人手不足を補うために創設された在留資格で、外国人が日本で働くことを目的としています。特定技能1号(熟練前)と特定技能2号(熟練技能者)の2種類があります。
-
特定技能1号と2号の違いは何ですか?
-
1号は最長5年の在留が可能で、家族帯同はできません。2号は在留期間の更新が可能で、家族帯同も認められています。また、2号の就労期間は、永住許可申請に必要な就労期間としてもカウントできます。
-
技能実習と特定技能の違いは何ですか?
-
技能実習は「発展途上国への技能移転」が目的で、学びながら働く制度です。一方、特定技能は「即戦力としての就労」が目的で、給与や待遇も日本人と同等が求められます。技能実習を経て特定技能に移行するケースも一般的となっています。
-
他の在留資格から特定技能に変更できますか?
-
はい、可能です。ただし、希望する分野の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。実際に就労先が確保できた場合には、在留資格変更許可申請が必要となります。
-
「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。
-
特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、特定技能1号より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。ですので「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、各分野の経験年数や試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
-
特定技能者への支援は誰が行いますか?
-
受入れ企業は、特定技能外国人の支援計画を定め、この計画に従って支援を行います。実施方法は、企業が自ら行うか、登録支援機関に委託するかを選べます。必須支援10項目を確実に実施することが求められます。
-
在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
-
特定技能外国人が、従事しようとする業務に対応する技能を有している場合、転職可能となります。転職に当たり、受入れ機関を変更する場合は、特定技能ビザの変更許可申請を行う必要があります。
まとめ
まとめ
特定技能は、日本の特定の産業分野における深刻な人手不足を補い、外国人が日本で安心して働けるよう設けられた重要な制度です。
技能や日本語能力の証明、適切な雇用契約、そして企業による支援体制の整備が求められますが、これらをクリアすることで、企業の皆様も外国人の方も安心して受入れ/就労が可能となります。具体的な受入れ/就労手続きについて、登録支援機関や専門の行政書士へ相談されることも検討してみてください。制度の仕組みや要件、支援体制について正しく理解し、スムーズな受入れ/就労を目指しましょう。
【当事務所が提供する特定技能サポート業務】
当事務所では、特定技能外国人支援経験のある行政書士スタッフにより、以下のサービスをご提供させていただいております。
●特定技能外国人登録支援機関業務
・特定技能1号外国人の生活・就労に係る10項目の支援業務(全部委託・一部委託いずれも可能です。)
・特定技能1号外国人の定着サポート業務
●自社支援導入サポート業務
●在留資格申請業務(支援計画作成サポートを含む)
●入管届出書類の作成サポート業務
○ 随時の届出
- 雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
- 支援計画の変更に係る届出
- 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
- 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
○ 定期の届出
- 特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出
- 支援計画の実施状況に関する届出
●分野別の申請/登録等のサポート業務
◯建設
外国人就労管理システム登録サポート
◯介護
- 特定技能協議会への入会申請及び「訪問介護」適合確認申請書類作成サポート(国際厚生事業団(JICWELS))
- 各都道府県への補助金申請業務サポート
当事務所へ各種サポートのご依頼をご検討中の方
ぜひ一度無料相談を利用ください。
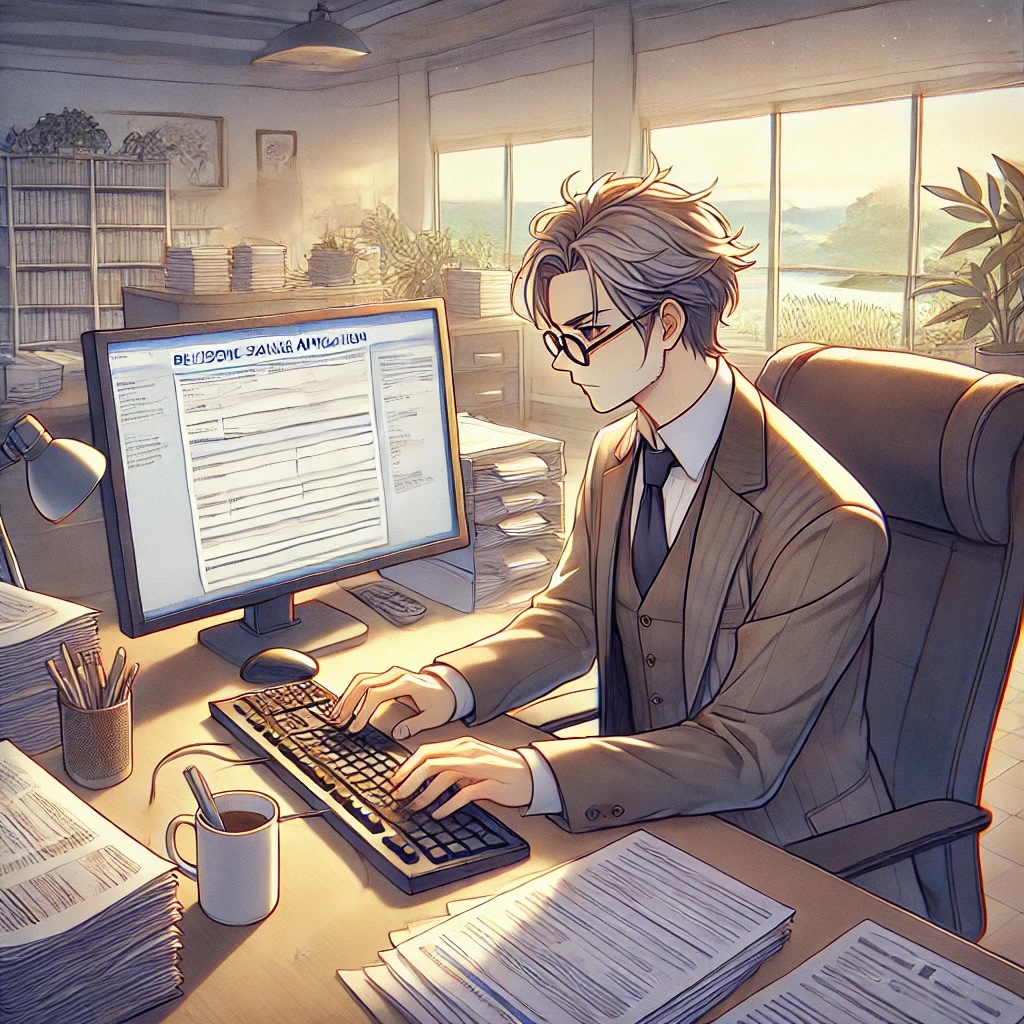
記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
