
「日本でずっと暮らしたい」――そんなあなたへ
永住を目指す方にとって必要となるのが、「永住者」という在留資格、いわゆる“永住ビザ”です。
しかし、いざ申請となると、「何を準備すればいいの?」「書類がたくさんあって混乱する…」「本当に許可がもらえるのかな…」と、不安や疑問を感じる方も少なくありません。
このページでは、日本での永住を希望される方が安心して申請手続きに取り組めるよう、永住申請の主な条件、必要書類の一覧と取得方法、不許可を避けるためのポイントなどをまとめました。
ご自身やご家族の将来のために、ぜひじっくりとご覧ください。
▶ 気になるところから読めます!
永住ビザってどんなビザ?
永住ビザってどんなビザ?
「永住ビザ(永住者)」とは、日本に長期間住み、安定した生活基盤を築いている外国人に対して認められる在留資格です。この永住ビザを取得することで、在留期間の制限がなくなり、在留資格の更新手続きも不要になります。また、就労の制限もなく、自由に働くことができるようになります。
日本での暮らしを長期的に続けたい外国人にとって、永住ビザは非常に魅力的な資格です。特に、家族と共に安心して日本に定住したい方や、仕事の選択肢を広げたい方にとって、永住ビザの取得は大きなメリットとなります。
永住ビザは、単に日本に長く住んでいるというだけで取得できるものではなく、これまでの在留状況や収入、納税、社会保険加入など、さまざまな条件が審査されます。そのため、正しい知識と十分な準備が必要です。
この記事では、「永住権」「永住資格」「永住ビザ」などと呼ばれるこの在留資格について、「永住ビザ」という用語を使って解説していきます。
【永住ビザのメリット】
- 在留期間の制限がなくなる:永住ビザを取得すると、これまでしてきた期間更新手続きすることなく日本に滞在できます。
- 活動の制限がなくなる:どのような職業にも就くことが可能となります(一部の職業を除く)。
- 社会的信用が高まる:永住ビザを持っていると、住宅ローンやクレジットカードの審査が通りやすくなるなど経済面での信用が高まります。
- 家族の生活安定:永住者の配偶者や子どもも、比較的簡単に在留資格を取得・維持しやすくなります。
- 母国での権利は失わない:国籍の変更はないことから、母国にて付与されている権利を失うことはありません。また日本を一時的に離れる際も、再入国許可を受ければ一定期間日本国外に滞在することも可能です。
- 社会保障制度へのアクセス:永住者は他の外国人と同様に、日本の社会保障制度(健康保険、年金など)を引き続き利用できます。
- 経済的メリット:永住者になると、ビジネスや投資の自由度が増します。自営業や会社設立をする際も、特別な制限を受けずに活動できます。
- 帰化申請の準備段階:永住者資格は、日本国籍を取得する「帰化」の要件を満たすためのステップとしても有用であると言えます。
【永住ビザの審査】
永住者の在留資格(永住ビザ)は、誰でも簡単に取得できるものではありません。
申請者が日本で法令を遵守し、経済的に安定して生活していけるかどうかを厳しくチェックします。
具体的には、これまでの在留歴や素行、収入・納税状況、社会保険の加入状況などが総合的にチェックされます。
また、提出書類についても、法務省が公表している「必要書類一覧」だけでは不十分なことがあり、個別の事情に応じて追加資料が必要となります。
ご自身で申請することも可能ですが、書類の不備や説明不足により不許可となるリスクもあるため、永住ビザ申請に詳しい行政書士に相談・依頼することも有効な選択肢です。
ビザの取得に必要な要件とは?
ビザの取得に必要な要件とは?
永住者の在留資格を取得するためには、以下の主な要件を満たす必要があります。
【日本に住んでいる年数】
原則として、申請者は引き続き10年以上日本に居住しており、かつ直近の5年以上、就労可能な在留資格で在留している必要があります(特定技能1号と技能実習を除く)。
また以下の場合は居住10年の要件が緩和されます。
- 日本人や永住者の配者である場合:婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること
- 定住者の在留資格で日本に住んでいる場合:5年以上日本に居住していること
※1回の出国が90日以上、または年間100日を超える出国は、居住要件の年数がリセットされるリスクが高まるので、出国日数には十分な注意が必要です。
【安定収入もしくは相応の資産があること】
日本で生活していくために必要な安定収入や資産があることです。
収入の目安は、単身者の場合年収300万円程度で、扶養者が増えるごとに一人当たり60万円程度を加算た金額が目安の年収が必要となります。
申請人ご本人に安定収入がなくても、同居している配偶者や親に安定収入や資産がある場合、 永住ビザを取得できる可能性があります。
一方で生活保護を受けている場合などは、永住ビザの取得は非常に難しくなります。
【素行が善良であること】
前科または少年法による保護処分歴がないこと、および納税等の公的義務を履行していることなどが求められます。
また、道路交通法の違反者になっていないことなども要件となります。その他、日常生活において も住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。
永住ビザ申請の必要書類
永住ビザ申請の必要書類
【現在お持ちのビザが就労するためのビザの場合】
共通申請書類
- 永住許可申請書
- 証明写真
- 在留カード/パスポートの写し
- 永住許可を必要とする理由書
- 申請人を含む家族全員の住民票
- 健康保険被保険者証の写し
- 身元保証書
- 了解書
- 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
- 「在職証明書・確定申告書控えの写し・営業許可書の写し・職業に係る説明書及びその立証資料」のいずれかの書類
- 国税の納税証明書
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書などの資料
技術・人文・国際業務 などの方の申請書類
- 住民税の課税(又は非課税)証明書(直近5年分)
- 住民税の納税証明書 (直近5年分)
- 住民税を適正な時期に納めていることを証明する通帳の写し等(住民税が給与から天引きされていない方(直近5年分))
- ねんきん定期便又はネットの「各月の年金記録」の印刷画面 (直近2年分)
- 国民年金保険料領収証書の写し(直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方(直近2年分))
- 国民健康保険料納付証明書(国民健康保険に加入している方 (直近2年分))
- 国民健康保険料領収証書の写し(国民健康保険に加入している方 (直近2年分))
- 健康保険/厚生年金保険 料領収書の写し直近2年分。または社会保険料納付証明書又は社会 保険料納入確認(申請)書(直近2年分)
高度専門職又は特定活動の方の申請書類
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(80ポイント以上の方のみ)
- 高度専門職ポイント計算に 係る疎明資料
- 住民税の課税(又は非課税)証明書 →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近3年分
- 住民税の納税証明書 →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近3年分
- 住民税を適正な時期に納めていることを証明する通帳の写し等(住民税が給与から天引きされていない方) →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近3年分
- ねんきん定期便又はネットの「各月の年金記録」の印刷画面 →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近2年分
- 国民年金保険料領収証書の写し(直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方) →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近2年分
- 国民健康保険料納付証明書(国民健康保険に加入している方)(直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は不要) →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近2年分
- 国民健康保険料領収証書の写し(国民健康保険に加入している方)(直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は不要)→80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近2年分
- 健康保険/厚生年金保険 料領収書の写し、または社会保険料納付証明書又は社会 保険料納入確認(申請)書 →80ポイントの方は直近1年分・70ポイントの方は直近2年分
【現在お持ちのビザが日本人の配偶者等や定住者ビザなどの場合】
共通申請書類
- 永住許可申請書
- 証明写真
- 在留カード/パスポートの写し
- 申請人を含む家族全員 の住民票
- 健康保険被保険者証の写し
- 国民健康保険被保険者証の写し(国民健康保険に加入している方)
- 身元保証書(身元保証人様が作成します)
- 身元保証書に係る資料(運転免許証、在留カードの写し等)
- 了解書
- 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料
- 「在職証明書・確定申告書控えの写し・営業許可書の写し・職業に係る説明書及びその立証資料」のいずれかの書類
- 国税の納税証明書
【身分系在留資格ごとの申請書類】※必要書類は在留資格によって異なります。
- 永住許可を必要とする理由書
- 親族一覧表
- 戸籍等関係書類
a. 配偶者の戸籍謄本
b.日本人親の戸籍謄本
c.配偶者との結婚/婚姻証明書等
d.出生証明書等
e. 上記a~dのいずれかの書類等
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など
※以下の資料の必要年数は、現在の在留資格により異なります。
- 住民税の課税/非課税証明書
- 住民税の納税証明書
- 住民税を適正な時期に納めていることを証明する通帳の写し等
- ねんきん定期便又はネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料領収証書の写し(直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方)
- 国民健康保険料納付証明書(国民健康保険に加入している方)
- 国民健康保険料領収証書の写し(国民健康保険に加入している方)
- 健康保険/厚生年金保険 料領収書の写し。または社会保険料納付証明書又は社会 保険料納入確認(申請)
審査期間はどのくらい?
審査期間はどのくらい?
永住許可申請の審査期間は、通常4か月から1年程度かかります。
審査期間は申請内容や個別の状況により異なり、以下の要因が影響することがあります。
【審査期間に影響する要因】
- 提出書類の正確性と充実度:書類に不備がある場合や、追加資料の提出を求められた場合は審査が長引くことがあります。
- 申請者の経歴や状況:長期間にわたり安定した収入や納税が確認できる場合、比較的スムーズに審査が進む傾向があります。また在留歴に特記事項(例:オーバーステイや資格外活動の履歴など)がある場合、慎重な審査が行われる可能性があります。
- 入管の混雑状況:申請が集中する時期(年度末や新年度)や、入管の業務量によって審査期間が延びる場合があります。
- 家族全員で申請する場合:家族分の審査が必要なため、単身で申請する場合より時間がかかることがあります。
【審査状況の確認】
申請後、入管局で発行される「受付票」に記載された番号を使って、申請状況を確認することができます。ただし、具体的な進捗は入管から通知されないことが多いため、結果が出るまで待つしかありません。
永住ビザが不許可になるケースとは?
永住ビザが不許可になるケースとは?
【必要な条件を満たしていない場合】
- 在留期間が不足している場合:通常、日本に10年以上継続して在留している必要があります(例外あり)。10年未満の場合、特例が適用される状況を満たしていないと不許可となります。特例として、日本人や永住者の配偶者、定住者などの場合、1年以上の婚姻や滞在歴が基準となります。
- 安定した収入や資産がない場合:低所得や無職が続いているなど生活基盤が不安定であると判断された場合、審査で不利になります。
- 納税義務を果たしていない場合:市民税や所得税、社会保険料の未納だけでなく、納期を守らなかったことも不許可の原因となります。
【法律違反や社会的信用の問題】
- 過去に犯罪や違法行為を行った場合:交通違反(飲酒運転など)を含む法律違反があると、永住許可が難しくなります。特に、罰金刑や懲役刑の履歴がある場合は重大な影響があります。
- 資格外活動やオーバーステイの履歴:在留資格の範囲を超えた活動(無許可での労働など)や、過去に在留期限を超過して滞在していた場合も審査に重大な影響があります。
【提出書類の不備や虚偽】
- 必要書類が不足している場合:指定された書類の提出が不完全な場合や正確な内容でない場合、追加提出等により審査が長引くだけでなく、最終的に不許可となってしまう可能性があります。
- 虚偽の情報を申告した場合:申請書や添付資料に虚偽の内容が含まれていると、不許可になるだけでなく将来の申請にも悪影響が及ぶ可能性があります。
【社会的信頼性の欠如】
- 頻繁に転退職している場合:安定した職業に就いていない場合、経済的基盤が脆弱と判断される可能性があります。
- 家族の扶養状況に問題がある場合:扶養している家族が適切に生活できていない場合や、家族が社会保険に未加入である場合なども審査に影響します。
【不許可後の対応】
不許可となった場合でも再申請は可能です。ただし、不許可理由をしっかり確認し、改善点を明確にしたうえで再度申請する必要があります。不許可理由は原則として入管で開示されるため、確認をおすすめします。
永住ビザに関するよくあるご質問(FAQ)
永住ビザに関するよくあるご質問(FAQ)
-
永住ビザを申請するには、どのくらい日本に住んでいなければなりませんか?
-
原則として、「引き続き10年以上」日本に在留している必要があります。そのうち5年以上は就労資格(例:技術・人文知識・国際業務など)または居住資格(例:日本人の配偶者等)での在留が必要です。ただし、日本人の配偶者や高度人材などには例外もあります。
-
永住ビザを取得すると、どんなメリットがありますか?
-
最大のメリットは、在留期間の更新が不要になり、活動制限もなくなることです。職種や雇用形態に関係なく働けるようになるほか、社会的信用が高まり、住宅ローンや各種契約でも有利になる場合があります。
-
永住ビザの申請中に現在の在留資格が切れそうです。どうすればいいですか?
-
永住ビザを申請しても、現在の在留資格が自動で延長されるわけではありません。現在の在留資格の更新手続きも忘れずに行う必要があります。更新せずに期限を過ぎると、不法滞在となってしまいますので注意が必要です。
-
永住ビザの申請に必要な収入はいくらですか?
-
明確な金額は法令では定められていませんが、概ね年収300万円以上がひとつの目安とされています。扶養家族がいる場合は、その人数に応じてより高い安定収入が求められます(扶養家族1人につき60万円から70万円)。また、納税状況や社会保険加入もあわせて審査されます。
-
自分で永住ビザの申請はできますか?行政書士に依頼する必要はありますか?
-
もちろん、ご自身で申請することは可能です。ただし、永住申請は必要書類が多く、個別事情によっては追加書類や説明資料が求められるため、専門の行政書士に依頼することで不許可リスクを減らせる場合もあります。
まとめ
まとめ
【永住ビザを目指す方へ - 専門家のサポートも選択肢に】
在留資格「永住者」は、日本国内で長期にわたり安定した生活を送り、日本社会に貢献している外国人に与えられる特別な資格です。永住ビザを取得すれば、在留期間の制限がなくなり、職業や活動内容にも制限がなくなるなど、多くのメリットがあります。しかし、その一方で、申請には多くの書類を適切に揃え、内容に一貫性・整合性があるかを自分でチェックしなければなりません。特に収入や納税履歴、在留状況などの審査では、細かな説明や補足書類が必要になるケースもあります。こうした手続きに不安がある方は、入国管理局の審査基準や実務に精通した行政書士に相談・依頼することで、不許可のリスクを大きく減らすことができます。ご自身の状況に合わせて、専門家のサポートも一つの選択肢として、ぜひご検討ください。
【当事務所へ手続きをご依頼いただいた場合のサービス内容】
~ 在留資格の申請をトータルでサポートいたします ~
- ご相談とお客様の詳細な状況のヒアリング(初回無料)
- ビザの取得可能性のご案内
- 必要な書類や手続きの流れのご案内
- 必要な書類のアレンジと申請書・理由書・説明書など各種補強資料の作成
- 公的書類の取得方法のご案内
- 入管への申請代行(東京入管・名古屋入管のみ)
- 入管からの追加資料要求への対応
【特にこんな方におすすめ!】
- 初めてのビザ申請で不安な方
- 書類の書き方や理由書の作成に自信がない方
- ご事情が複雑な方
- お時間のない方
当事務所へ申請手続きの依頼をご検討中の方
ぜひ一度無料相談を利用ください。
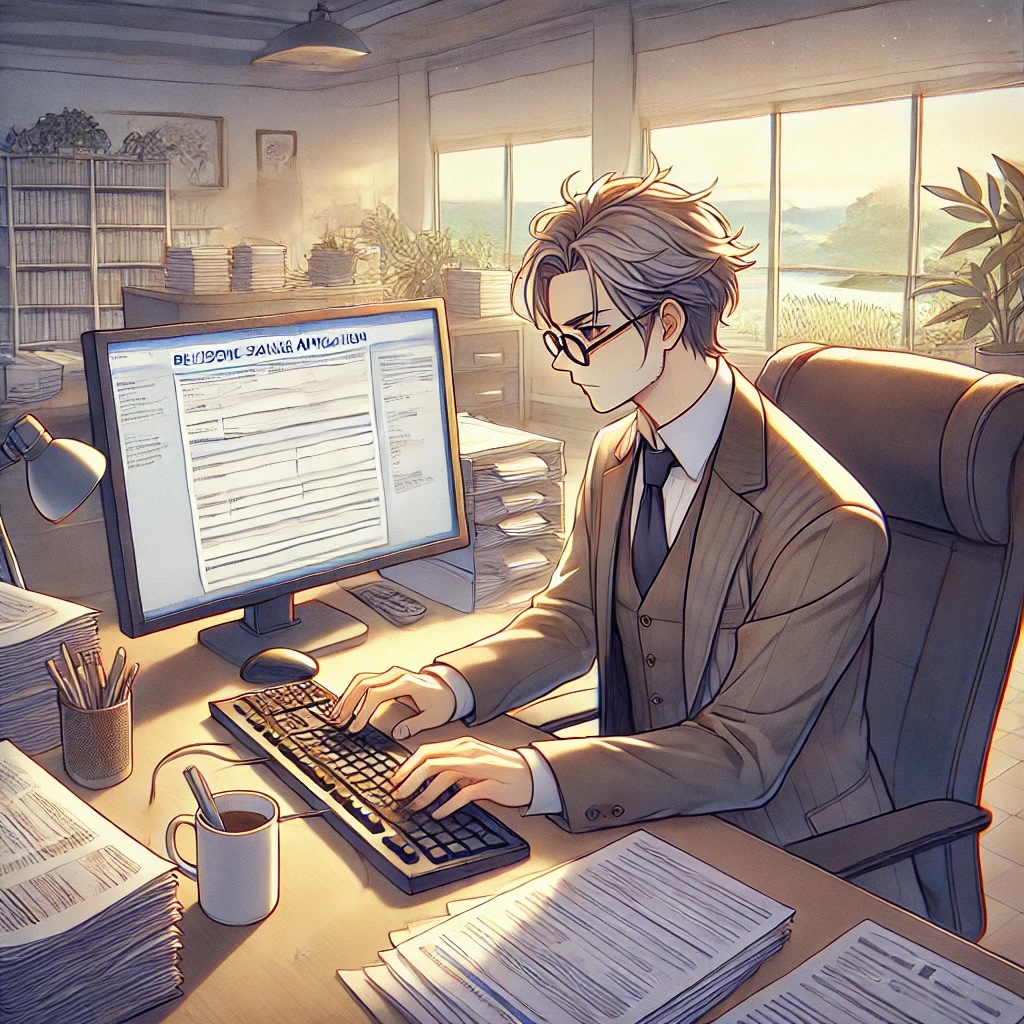
記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
