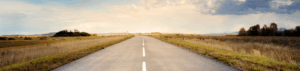
日本でご家族と共に暮らしたい方、日本に根を下ろして新たな人生を歩みたい方にとって、「定住者ビザ」はとても重要な在留資格です。
このビザは、条件さえ揃えば、ご事情に応じて柔軟に対応できる在留資格であり、日本での生活を安定させる大きな支えとなります。
中でも、「連れ子定住ビザ」や「離婚定住ビザ」は、人生の節目に関わる大切な申請です。
たとえば再婚相手のお子様を日本に呼び寄せる場合や、日本人の配偶者と離婚後も日本で暮らし続けたい場合などご事情はさまざま。
当事務所では、丁寧なヒアリングを通じて、お一人おひとりの背景やお気持ちに寄り添い、適切な書類の作成と手続きを全力でサポートいたします。
▶ 気になるところから読めます!
定住者ビザってどんなビザ?
「定住者ビザ(在留資格:定住者)」は、外国人が日本で中長期的に安定して生活することを可能にする非常に柔軟性の高い在留資格です。
これは他の就労系や身分系の在留資格と異なり、法務大臣が申請人の特別な事情を個別に考慮し、居住を認める在留資格として設けられています。
他の在留資格ではカバーしきれない背景や事情を持つ外国人のための“救済的”な資格ともいえます。
「定住者」検索すると、多くの方が「明確な条件がない」と困惑するかもしれません。
実際、定住者ビザには他の在留資格のような画一的な要件が規定されていません。
そのため、審査は大変厳しく、申請には丁寧な説明や証明が求められます。
審査では、申請者のこれまでの日本での生活状況や家族構成、生活基盤、経済状況、今後の生活設計などが総合的に判断されます。
ポイントは、「この人が日本で定住することに十分な理由があるか」を、入管に納得してもらえるかどうかがカギです。
定住ビザの取得の基本的な要件とは?
【日本との特別な関係があること】
日本人の元配偶者である外国人、日系人、元難民など、日本との特別な関係がある外国人。
【生活の基盤が安定していること】
安定した生活を送ることができる経済基盤があることが重要な要件となります。身元保証人は、収入が安定し、家族を扶養する能力があることも重要な要件であり、加えて生活のための住居を確保していることも必要です。
【素行が良好であること】
申請人は、国内で法律や規則を守り、社会的に良好な素行を維持していることが重要です。申請人が過去に重大な犯罪や違法行為をしていた場合、定住資格の取得は難しくなります。
【その他特定の事情】
申請者の個別の事情により、特別な理由で定住が認められることもあります。
【告示定住】
「告示定住」とは、出入国在留管理庁が告示で定めるケースを指します。
⽇系⼈
- 告⽰3号︓⽇本⼈の⼦として出⽣した者の実⼦(孫)で素⾏が善良
- 告⽰4号︓⽇本⼈の⼦として出⽣した者で、かつて⽇本国⺠として本邦に本籍を有したことがある者の実⼦の実⼦であって素⾏が善良
定住者の配偶者/⽇本⼈配偶者等ビザを持つ者の配偶者
- 5号イ︓「⽇本⼈の配偶者等」ビザを持つ者の配偶者
- 5号ロ︓3号/4号以外の定住者ビザを持つ者の配偶者
- 5号ハ︓3号/4号の定住者ビザを持つ者の配偶者で素⾏善良
⽇本⼈/永住者/定住者/の未成年の実⼦
- 6号イ︓⽇本⼈、永住者/特別永住者の扶養を受けて⽣活する未成年で未婚の実⼦
- 6号ロ︓1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて⽣活する未成年で未婚の実⼦
- 6号ハ︓3号/4号の定住者ビザを持つ者、⼜は3号/4号の配偶者たる定住者ビザを持つ者で1年以上の在留期間を指定されている者の扶養を受けて⽣活するこれらの者の未成年で未婚の実⼦であって素⾏が善良
- 6号ニ︓日本人・永住者、特別永住者、または1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者のうち、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格をもつ者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
⽇本⼈/永住者/定住者/の6歳未満の養⼦
7号イ〜⼆︓⽇本⼈、永住者、⼀年以上の在留期間を指定されている定住者、特別永住者の6歳未満の養⼦
【告示外定住】
「告示外定住」とは、個別の事情を考慮して定住者として認められる在留資格のことです。個別の理由を詳細に説明し証拠を提出する必要があります。
- 日本人の配偶者と離婚または死別した外国人で、引き続き日本で生活する事情がある場合
- 永住者の配偶者と離婚した外国人で、引き続き日本での生活が必要と認められる場合
- 特別な人道的配慮が必要な外国人
- ほか
連れ子定住ビザとは?
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した外国籍の方が、自分の実子(連れ子)を日本に呼び寄せたい場合、その子どもは、定住者ビザを申請することになります。
このビザは、定住者告示の「第6号ニ」に該当し、連れ子ビザとも呼ばれます。
【連れ子ビザの申請条件】
- 外国人夫または妻が「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていること
- 呼び寄せたい子どもが未成年(18歳未満)かつ未婚の実子であること
- あなたと子どもの親子関係が証明できること(戸籍や出生証明書など)
- 子どもが来日後、扶養される予定であること(就労目的ではない)
- 世帯収入や住居環境など、日本での扶養体制が整っていること
【申請時に重視されるポイント】
- 親子の扶養実績:過去に本国でどのように扶養していたか、生活の面倒を見ていたかなどが問われます。
- 婚姻関係の実態:内縁関係では原則として申請できません。まずは正式な婚姻手続きを完了させていることが前提となります。
- 経済的な支援体制:日本における生活費、教育費などをまかなう経済的基盤があるかどうかが審査されます。
- 子どもの年齢と就労目的の有無:子どもが18歳に近い場合、「実際は就労目的ではないか」と疑われるリスクが高くなります。
- 日本での同居予定:原則として、来日後はあなた方夫婦と連れ子が同居することが求められます。
- 呼び寄せのタイミング:外国人夫または妻が配偶者ビザ取得から時間が経っている場合、その間の扶養実績や理由について、より丁寧に説明する必要があります。
【ビザの申請】
連れ子ビザ(定住者告示6号ニ)は、親子としての生活を日本で実現するための大切な制度ですが、その分、申請には細やかな配慮と十分な準備が必要です。「未成年」「未婚」「扶養」「同居」といった基本条件を満たすことはもちろん、申請書類の一つひとつに、合理的かつ説得力のある説明を添えることが、不許可を防ぐカギとなります。
【連れ子定住ビザに関するよくある質問(FAQ)】
-
実の親がすでに日本で「日本人の配偶者等」として暮らしていますが、子どもを日本に呼び寄せることはできますか?
-
はい、可能です。連れ子の方が未成年で未婚の実子であること、日本で暮らす親が実際に監護・養育する意思と能力があることなどが条件となります。
-
どんな場合に「連れ子定住ビザ」が認められやすくなりますか?
-
実親と連れ子の関係が明確であり、来日前から養育実績がある場合や、離れて暮らしていても仕送りや頻繁な連絡が継続していた場合は認められやすい傾向にあります。また、日本での生活基盤(住居・収入)が安定していることも重要です。
-
どのような書類を用意すればよいですか?
-
扶養者の戸籍謄本・連れ子さんの出生証明書・親権証明書、日本での生活状況を説明する資料、扶養能力を証明する書類などが基本となります。
-
離れて暮らしていた期間が長いのですが、呼び寄せることはできますか?
-
長期間別居していた場合でも、過去の養育実績や定期的な仕送り、連絡記録などがあれば、審査にプラスになります。実質的な親子関係を立証することが重要となります。
連れ子定住ビザ申請に必要な書類
外国人夫または妻の連れ子を海外から招くに必要な書類は以下のとおりです。
【共通書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真
【扶養する方に関する書類】
- 扶養者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 扶養者が会社に勤務している場合の在職証明書
- 扶養者の確定申告書の控えの写し(自営業等の場合)
- 扶養者の営業許可書の写し(自営業等の場合)
- 日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し(扶養者が無職の場合)
【その他】
- 身元保証書
- 理由書
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
- 家族で写った画像
- SNSやメールのメッセージ記録
※その他、家族の状況に応じた書類
離婚定住ビザとは?
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在している外国人の方が、離婚したあとも引き続き日本で暮らしたいと希望する場合、現在の配偶者ビザのままでは在留できなくなります。このようなケースで検討されるのが、いわゆる「離婚ビザ」または「離婚定住ビザ」と呼ばれる定住者資格です。実際には、「定住者(告示外)」への在留資格変更という手続きになります。離婚という人生の大きな転機に伴うビザ変更という手続きは、不安と戸惑いの連続かもしれません。しかし、「離婚定住」という在留資格は、これまで日本で築いてきた生活を守るための選択肢でもあるので落ち着いて手続きを進めましょう。
【離婚後の在留資格の検討】
技人国ビザや特定技能ビザへの変更申請もできなくはありませんが、学歴/経歴の面などでで要件を満たすことが困難な場合が多いと思います。そのため多くの場合、総合的な事情を考慮したうえで審査される柔軟な在留資格である離婚定住ビザが主な選択肢となります。なお、離婚後は、14日以内に、申請人の住所を管轄する出入国在留管理局へ「所属機関等に関する届出」を提出しましょう。
【離婚定住ビザの申請条件】
- 3年以上の実態のある婚姻期間が継続していた:婚姻の実態があり、一定期間日本で夫婦として生活していたことが重視されます。短期間の婚姻では「形だけの結婚」と疑われやすく慎重は審査となります。
- 公的義務をきちんと果たしている:住民税や社会保険の支払い義務等を履行し、加えて犯罪などの法令違反がないことが求められます。
- 安定した収入または資産がある:経済的に自立して生活していけるかどうかも重要な審査ポイントです。無職だった場合は、ただちに就労先を確保したうえで雇用契約を締結し、将来の生計の見込みを証明する必要があります。
- 日本での在留を希望する合理的な理由がある:長期間の日本で生活により、地域社会と強固なつながりがある、仕事が日本にある、子どもが日本で学校に通っている…など、「なぜ日本に残る必要があるのか」について、具体的に説明できることが求められます。
【離婚後の留意点】
離婚後6ヵ月を超えても在留資格の変更を行わないと、配偶者ビザの取消し対象(入管法第22条の4)となる可能性があるため、早めの離婚定住ビザへの変更申請手続きが重要です。
【その他】
- 原則として身元保証人が必要です(友人・雇用主などが該当可)
- 子どもがいる場合、親権の有無や扶養状況がビザ審査に大きく影響します
- DV被害など特別な事情がある場合、個別対応になることもあります(人道的配慮)
【離婚定住ビザに関するよくある質問(FAQ)】
-
離婚しただけで、自動的に定住者ビザに変更できますか?
-
いいえ、離婚しただけでは自動的に「定住者」へ変更されることはありません。離婚後も日本に滞在するためには、入管に対して「定住者」への在留資格変更申請を行い、正当な理由や生活基盤があることを示す必要があります。
-
離婚からどれくらいの期間で申請すべきですか?
-
離婚後、在留資格が「日本人の配偶者等」のまま放置していると、在留資格取り消しの対象となることがあります。なるべく早く(できれば3ヶ月以内)に定住者ビザへの変更申請を行うことをおすすめします。
-
離婚定住ビザの審査で重視されるポイントは何ですか?
-
主に以下の点が重視されます:
- 日本での生活実績(居住年数、就労歴など)
- 経済的自立(安定した収入や仕事)
- 日本社会とのつながり(子どもの養育、日本語能力など)
- 離婚に至った経緯とその後の生活計画
-
子どもがいない場合でも、離婚定住ビザは取得できますか?
-
子どもがいない場合でも、その他の事情(日本での長期間の生活、日本語能力、安定した仕事や生活基盤)があれば、定住者ビザが認められる可能性はあります。ただし、申請書類や理由書などで、しっかりとご自身の状況を説明することが非常に重要です。
離婚定住ビザ申請に必要な書類
離婚定住ビザ申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真
- パスポートと在留カードの写し
- 前配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 離婚届受理証明書
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 会社に勤務している場合の在職証明書
- 会社に勤務している場合の雇用契約書
- 会社に勤務している場合の給与明細書
- 確定申告書の控えの写し(自営業等の場合)
- 営業許可書の写し(自営業等の場合)
- 預貯金通帳の写し
- 身元保証書
- 申請理由書ほか補足説明資料
- 上申書・嘆願書等
※その他ご家庭の状況に応じた書類
審査期間はどのくらい?
連れ子定住、離婚定住ともに、入管での審査期間は、概ね2か月から3か月程度ですが、状況により1ヶ月で許可される場合や4ヶ月以上かかある場合もあります。審査が無事に終了すると、「定住者」の在留資格が許可され、在留カードに「定住者」として記載されます。
不許可になりやすいケースとは?
【連れ子定住ビザ】
- 親子関係・扶養関係が希薄な場合
連れ子さんと配偶者の間に扶養の実績がない場合や「親子の実態」が不明確な場合 - 未成年であるものの年齢が高い場合(高年齢の子どもを呼び寄せる場合、「働かせる目的では?」と疑われやすい)
- 扶養者の経済力が不十分で呼び寄せ後の生活を支える経済基盤が不安定と判断される場合
- 説明資料や証明資料が不十分な場合(なぜこのタイミングで呼ぶのかの説明が曖昧な場合など)
- 書類の不備や齟齬が多い場合(翻訳ミス、矛盾) など
【離婚定住ビザ】
- 婚姻期間が短すぎる場合(結婚から1年未満、同居期間が極めて短い場合など)
- 実態のある同居の証拠がない場合(離婚する前にすでに別居していたなど)
- 日本での自立が見込めない場合
- 離婚の経緯が不自然な場合(DVや別居理由に矛盾があるなど)
- 犯罪歴がある場合
- その他日本にいる正当な理由が見当たらない場合 など
まとめ
定住者ビザの申請は、他の在留資格に比べ、特に十分な準備と正確な書類作成が不可欠です。
自分で申請する場合、多数の書類を時系列や理由に沿って整合性を保ちながら揃えることは非常に難しく、ミスや漏れが不許可の原因となりやすいです。
不許可リスクをできるだけ減らすためには、入国管理局の審査に精通し、適切な書類作成や手続きを行える行政書士への依頼がおすすめです。専門家のサポートでスムーズな申請を目指しましょう。
【当事務所へ手続きをご依頼いただいた場合のサービス内容】
~ 在留資格の申請をトータルでサポートいたします ~
- ご相談とお客様の詳細な状況のヒアリング(初回無料)
- ご希望のビザの取得可能性のご案内
- 必要な書類や手続きの流れのご案内
- 必要な書類のアレンジと申請書・理由書・説明書など各種補強資料の作成
- 日本側で必要な公的書類の取得方法のご案内(住民票・課税証明書など)
- 本国での必要書類取得方法のご案内
- 入管への申請代行
- 入管からの追加資料要求への対応
- 本国での査証申請書作成サポート(認定証明書交付申請をされた場合)
【特にこんな方におすすめ!】
- 初めてのビザ申請で不安な方
- 書類の書き方や理由書の作成に自信がない方
- ご事情が複雑な方
- お時間のない方
当事務所へ申請手続きの依頼をご検討中の方
ぜひ一度無料相談を利用ください。
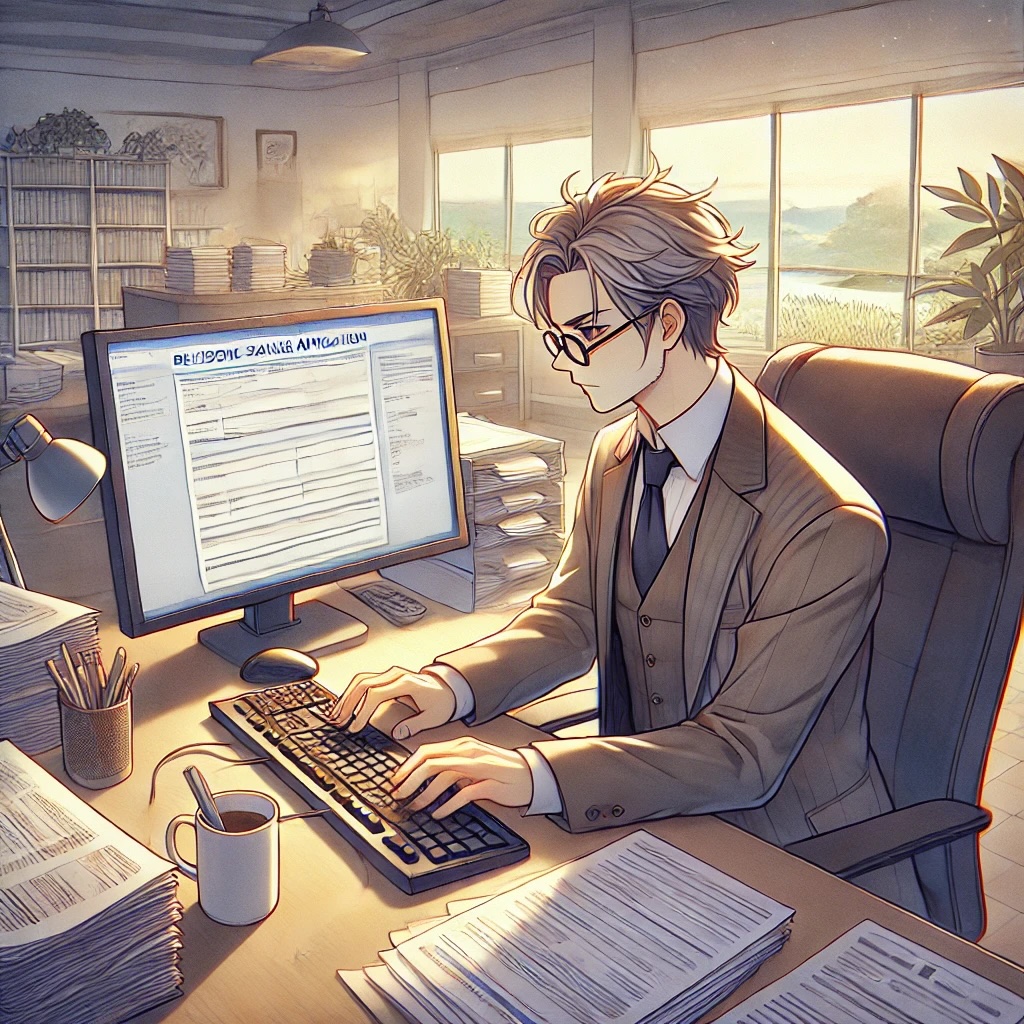
記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
